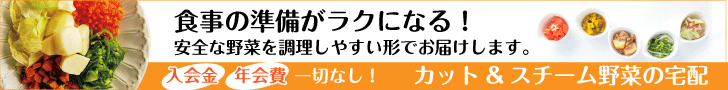あとがき
「誰かをケアするあなたへ」「心の居場所を探して」シリーズを最後まで読んでくださった皆さんへ。
心からのあとがきを、ここに綴ります。
ここまで読んでくださった皆さん、
本当にありがとうございます。
このシリーズでは、
「家族とは何か?」という問いを、
読んでくださる皆さんに投げかけるような気持ちで書いてきました。
自分の経験を書くことに、葛藤もありました。
ときどき、こんなふうに思われるかもしれません。
「家族を“だし”にして、自分の物語を書いているんじゃないか?」と。
でも、私は自分を「特別な存在」だとも、「悲劇のヒロイン」だとも思っていません。
ただ、
「被害者」にも「加害者」にもなり得る存在だとは思っています。
今も母は――
「無理やり施設に入れられて、娘(私)のせいで自分の生活が苦しくなっている」
と話していると、ケアマネさんから聞きました。
私はいま、距離を置くという選択をしています。
自分の心と身体を守るために。
私は、慰めてほしいわけでも、同情されたいわけでもありません。
ただ、自分の心と向き合い、前に進むために綴りました。
そしてなにより、
あの頃の自分と同じような境遇にいる「誰か」のために届けたい。
「ヤングケアラー」と一言で言っても、状況は様々です。
・親の病気や障がい
・兄弟の介護
・家事や看病、感情のケアまで背負ってしまうこと
――その形も、しんどさも、本当にいろいろです。
たとえば、私の母は「統合失調症」でしたが、症状の出方や向き合い方も人によって異なります。
だからこそ、この話はあくまで、
「ひとりの体験談」として、
「こんな人もいるんだ」くらいの気持ちで読んでもらえたら嬉しいです。
「もっと大変な人がいる」――その言葉が呪いになっていませんか?
私自身も、長いあいだ
「自分なんて大したことない」と引け目を感じていました。
「ヤングケアラー」という言葉を、最初は自分に当てはめるのに抵抗があったのかもしれません。
でも、その言葉を知っていなければ、支援先や相談窓口にすらたどり着けない。
まず知ることはとても大切なことだと思います。
孤独と孤立は、ちがいます。
私は、自分の気持ちや本当にやりたいことと向き合うためには
「孤独」は必要なものだと思っています。
けれど――
「孤立」は違う。
いくら家族でも、できることには限界があります。
これは、個人や家族の努力だけでは解決できないことです。
社会が見てこなかった「存在」が、ここにいます。
私はずっと、こんな感覚を抱いていました。
「いつもどこか社会から置き去りにされている感じがする」
「ヤングケアラー」は、社会から取り残されやすい存在だと思っています。
最近になってようやく、支援の輪が広がってきたことに希望を感じています。
最後に
どうかこのブログが、
あの頃の私と同じように苦しんでいる誰かのもとに、届きますように。
そして、
ヤングケアラーに理解ある社会に、少しずつ変わっていきますように。
🕊 あなたの気持ちに、そっと寄り添えたなら
ここまで読んでくださったあなたへ。
本当に、ありがとうございました。
🔗 関連リンク
シリーズ第1回へ戻る