はじめに
ヤングケアラーとして過ごした日々の中には、たくさんの「つらさ」がありました。
そんな中でも、小さな「嬉しさ」に救われた瞬間も確かにありました。
今回は、私自身がケアをしてきた中で感じたことを、いくつか綴ってみたいと思います。
もっと大変な人もいると言われて…
私には、伯母がいて何度か相談をしたことがありました。
母の統合失調症の症状が強く出て、見守りや家事、バイトが重なってつらくなり、
「話を聞いてほしい」と思って相談しました。
話は聞いてもらえて共感してくれる部分もあったけれど、最後に返ってきた言葉は、
「もっと大変な家庭もあるよ」。
看護師として色々な患者や家庭を見てきた伯母だからこそ出た言葉なのだと、
頭では分かっていたし、それは事実です。
でも「私の気持ちは受け止めてもらえなかった」と感じて、深く傷つきました。
その頃から、「本当に困ったときだけ相談しよう」と思うようになり、
人に頼ることがだんだんと難しくなっていきました。
「私なんて、まだ恵まれてる」
「もっと頑張らなきゃ、みんなつらさを背負って生きているんだから」
そんなふうに、自分を追い詰める言葉が、いつのまにか心に染みついていきました。
受験期に重なった”生活とケア”のプレッシャー
大学受験の時期、母の体調が悪化し、家の中の空気はとても不安定でした。
夜通し泣き続ける母、食欲を失い、お風呂の入り方がわからなくなる母…。
見守りながら、家事をこなし、限られた時間で勉強を続ける日々。
地元の国公立大学しか経済的に選択肢がなく、滑り止めもない中で、
私は推薦入試での合格を目指していました。
一般入試では多くの科目の勉強が必要で、見守りや家事と両立できる自信はありませんでした。
「もし落ちたら、管理栄養士の夢を諦めることになる」
その焦りやプレッシャーは、常に重くのしかかっていました。
周りの友達よりも勉強時間が少ないのでは…
そう思って、常に勉強していないと怖くなってしまっていました。
クラスの友達が、指定校推薦などで早々に進路を決めていく中、
私は、不安と焦りに押しつぶされそうでした。
突然、命に関わる判断を迫られるということ
これまで、母が錯乱状態になり、救急車を呼ばなければならないことが何度かありました。
離れて住む祖父母や伯母には相談していたけれど、
実際にその場で判断し、動かなければならないのは、同居していた私でした。
ある日、母は錯乱状態で混乱してしまっていて、
「入院につなげないと、このままでは私も弟も普通に生活できない」と思い、
伯母や祖父の助言もあって私は救急車を呼びました。
スマホを持つ手も、声もずっと震えてしまって、
過呼吸になりそうな自分をなんとか抑えて通報していました。
その日は、弟の卒業式の日でした。
朝のうちに、職場には休みの連絡を入れていたので、
母の代わりに弟の卒業式に本当は行ってあげたかった。
けれど、うちは車がないので、救急搬送で入院につなげるしかなくて。
駆けつけた救急隊の方に状況を説明して、
「入院までつなげたくて、病院まで連れて行ってもらえませんか」
すがるような思いでそう伝えると、私にそっと教えてくれました。
「“お母さんが自殺を図ろうとしている”ことを伝えると、入院につながりやすくなる」
「僕たちは、病院に連れていくことしかできないけれど……ごめんね」
それから無事に入院が決まり、手続きを済ませたあと、私は弟の卒業式には間に合いませんでした。
また、病院で医師にこれまでの母の症状や状態を詳しく伝えたり、入院のための手続きをしたりと、
疲弊してしまい、式に参加できる精神状態でもありませんでした。
制服姿で静かに家を出ていった弟を見送りながら、
「ごめんね」と「もう限界かもしれない」の両方を抱えていた日でした。
弟の「おいしい」が救いだった
そんな中でも、嬉しかったことがあります。
弟が、私の作った料理を「おいしい」と言ってくれたことです。
母の見守りや勉強に追われて、凝った料理は作れませんでした。
「ごめんね」と思いながら食卓に出したものでも、弟は残さずきれいに食べて、
「おいしかった」「また作って」と言ってくれました。
その言葉に、救われたような気持ちになると同時に、
「やっぱり私は、食で人を笑顔にしたい」と改めて思いました。
さいごに
あの頃を振り返ると、私は、「休むこと」や「助けを求めること」に罪悪感を抱いていました。
つらさを飲み込んで、「大丈夫」と言い聞かせることが習慣になっていました。
でも今、同じように進路や仕事、生活で悩んでいる人がいたら伝えたいです。
自分の心の声に、もっと耳を傾けていい。
自分の進みたい道を、選んでいい。
自分の人生は自分だけのものです。たった一度きりの人生を、誰かのために生きすぎないでほしい。
次回は、「その罪悪感、抱えすぎていませんか?」というテーマで、
私が感じていた罪悪感と、その手放し方についてお話しします。





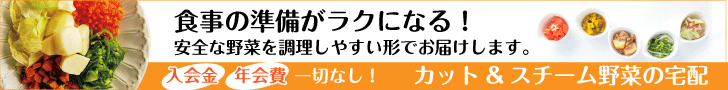
コメントを残す