「ヤングケアラー」って知っていますか?
ヤングケアラーとは、本来は大人が担うようなケアを、日常的に家族のために行っている子どもや若者のことです。
例えば、病気や障害のある親やきょうだいの介護・見守り、家事、感情のサポートなど。
見えづらいけれど、確かにそこにある”誰かのケア”を背負っている子どもたちです。
私はヤングケアラーでした
でも、当時の私は「ヤングケアラー」という言葉を知りませんでした。
母が統合失調症を抱えていることを打ち明けることもできず、学校ではなるべく”普通に”振る舞っていました。
「みんなもきっと何かを抱えている」
「みんな、つらさを見せていないだけ」
そう自分に言い聞かせていたけれど、どうしてみんな、あんなに笑っていられるんだろう?
なんで私はこんなにも苦しいんだろう?
もしかして、私が弱いだけ?
…そんなふうに、自分を責めてしまっていました。
もともと人に頼るのが苦手な性格でしたが、今思えば、耐えることが当たり前になっていて、誰かに話す、頼るといった選択肢は、当時の私の頭の中にはありませんでした。
「気づかれにくさ」があるからこそ、知っていてほしいこと
かつての私もそうだったように、ヤングケアラーは、自分自身を「ヤングケアラー」だと自覚していないことが少なくありません。
家族のお世話は当たり前のことだと思っていたり、本人はつらいとは思わずに日常のこととして行っていることもあるからです。
また、誰かに頼ることに慣れていなかったり、我慢することが当たり前になっていたりするため、「助けてほしい」と声をあげることができない子も多くいます。
だからこそ、周りの大人が気づくことが、とても大切です。
・いつも眠そうにしている
・イライラしたり、不安定な様子が続く
・家族のことを聞かれると話をそらす
・欠席や遅刻、早退が多い
そんな小さな変化の裏側に、実はケアの負担が隠れているかもしれません。
「もしかして」と思ったら、できること
「この子、もしかして…」
そう感じたとき、まず大切なのは”そっと見守ること”と”信頼関係を築くこと”です。
いきなり踏み込むのではなく、日常の中で話しかけたり、少しずつ距離を縮めたりしながら、安心できる関係を築いていくことが、なにより大切です。
そして、必要であれば専門機関につなぐことも、子どもを支える大人の大事な役割です。
このブログでも、今後そうした支援先の情報などを発信していきます。
知ることから、始めてみませんか?
「ヤングケアラー」という言葉が、もっと多くの人に届いてほしい。
そして、もし今まさにケアを担っている誰かが、ひとりでも「私だけじゃなかった」と思えたら嬉しいです。
次回は、ヤングケアラーとしての経験の中で感じた「つらかったこと・嬉しかったこと」を綴ります。
あなたのまわりにも、気づかれていない声があるかもしれません。





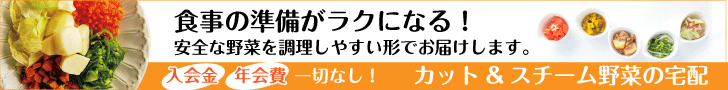
コメントを残す