伝えたいこと
ここまで読んでくださった皆さん、本当にありがとうございます。
このシリーズでは、「家族とは何か?」という問いを、読者の皆さんにそっと投げかけるつもりで綴ってきました。
もしかすると、これらの文章を「家族を“だし”にして、自分の経験を語っている」と感じた方もいるかもしれません。
でも私は、自分を“特別な存在”だとも、“悲劇のヒロイン”だとも思っていません。
ただ、人は誰しも――被害者にも、加害者にもなり得るのだと思っています。
今も、母は「無理やり施設に入れられて、娘のせいで自分の生活が苦しくなった」と話しているそうです(担当のケアマネジャーさんから聞きました)。
その言葉に、今でも胸がざわつきます。
それでも私は、今は距離を置いて、自分の心と身体を守るという選択をしています。
この文章は、慰めてほしくて書いたわけでも、同情を求めているわけでもありません。
自分の心と向き合い、前に進むために書いたものです。
そしてなにより――
あの頃の私と同じように、今もどこかで苦しんでいる誰かへ届けたくて。
「ヤングケアラー」といっても、その状況は本当にさまざまです。
精神疾患、がん、難病、知的障害、発達障害…
家族の抱える困難によって、子どもたちの“役割”は異なります。
さらに、成長してライフステージの変化とともに、家族のケアと子育て、介護なども同時に担う「ダブルケアラー」「トリプルケアラー」と呼ばれる人たちもいます。
私の体験も、「ひとつの例」にすぎません。
どうか、「こんな人もいるんだな」と思って読んでいただけたらうれしいです。
「自分はヤングケアラーに当てはまらない」と思っている方もいるかもしれません。
あるいは、その言葉を使うことに、引け目を感じる方も。
…実は、私もそうでした。
「もっと大変な人がいる」
その言葉が、まるで呪いのように心にまとわりついて、
苦しさを口にすることすらためらっていました。
でも、「ヤングケアラー」という言葉を知らなければ、
支援先を調べることも、相談することもできません。
私は思います。
ヤングケアラーと呼ばれる子どもたちは、社会から孤立しやすい存在だと。
最近になって支援の輪は広がってきましたが、
私が育った環境には、理解や助けの手はありませんでした。
まるで社会の中に「私の居場所」がないかのように感じていました。
いつも「どこか社会から取り残されている感覚」がありました。
私は、“孤独”はときに人生に必要なものだと思っています。
自分の気持ちや本当にやりたいことと向き合うために。
けれど、“孤立”は違う。
どれだけ家族でも、できることには限界があります。
これは個人や家庭の問題ではなく、
社会が“ヤングケアラー”を長く見過ごしてきたことの結果だと思うのです。
どうかこのブログが、
あの頃の私のように、ひとりで悩んでいる誰かの手に届きますように。
そして、社会が少しずつでも――
ヤングケアラーにとって優しく、理解のある場所へと変わっていきますように。








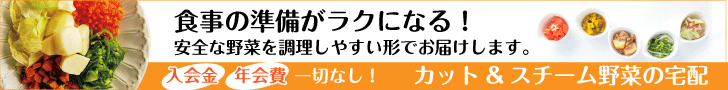
コメントを残す